質量分析計 (MS) と核磁気共鳴装置 (NMR) 、日本電子が描く分析の新しい姿 【JASIS2025出展レポート_Part1】
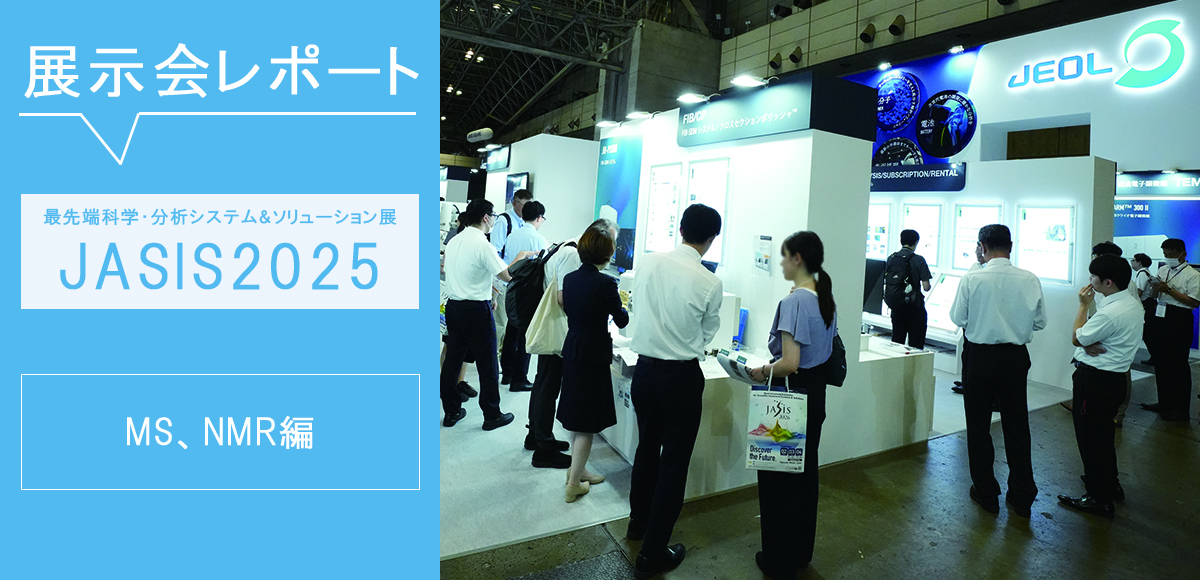
研究開発や産業の現場では、日々新しい化合物が誕生しています。医薬品、素材、食品、さらにはリサイクル分野に至るまで、幅広い領域で「未知の物質をいかに捉え、どう理解するか」が課題となっています。日本電子では、こうしたニーズに応えるため、質量分析計
(MS) および核磁気共鳴装置 (NMR) といった先端分析技術を提供しています。これらの技術は、物質の構造解析や定性・定量分析において高い信頼性と精度を誇り、日々の研究活動を支援しています。
本記事では、JASIS2025の説明員の声を交えながら、日本電子の最新の技術動向と、皆様の研究・開発にどのような価値をもたらすかをご紹介します。
「未知の物質解析」を実現するmsFineAnalysis AI Ver.3
今回JASIS2025にて日本電子が展示した「ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha」は、未知物質の構造解析に適した質量分析システムです。研究現場で求められる「高分解能」「多様なイオン化法」「AIによる解析支援」を一体化した本システムは、他成分混合試料中の化合物の同定や構造解明を、これまで以上に効率的かつ高精度に実現します。本システムの特長について、日本電子の佐藤はこう説明します。

日本電子の質量分析システムは、ハードウェア、イオン化技術、そして解析ソフトウェアを三位一体で提供する包括的なソリューションです。単に装置を納めるだけでなく、解析まで含めたサポートを行うことで、研究現場に大きな安心をもたらします。
このシステムには、三つの大きな特長があります。
第一に、高分解能測定が可能なハードウェアは、質量分析計の中でもトップクラスの性能を誇ります。
第二に、多彩なソフトイオン化(FI, PI, CI)法に対応し、分子イオンを壊さずにイオン化できるため、GC-MS標準の電子イオン化(EI)法と合わせて構造情報をより多く引き出せます。
第三に、取得したデータに含まれる未知物質はAIを活用した専用ソフトウェアで効率的に構造解析できます。
ここで重要なのは、「未知物質の構造解析」という観点です。データベースに登録のある既知物質であれば従来の装置でも対応可能ですが、未知物質の正体を明らかにするには、より高度な分解能、多様なイオン化の選択肢、そしてAIによる解析支援が不可欠です。日本電子の質量分析計は、まさにこの領域で力を発揮します。
そして今回、新たに登場した解析ソフトウェア 「msFineAnalysis AI Ver.3」 は、この解析力をさらに進化させました。最新のAIアルゴリズムを搭載し、従来よりも高速かつ高精度なデータ解析を実現。多成分を含むGC-MSのデータから構造情報を自動で抽出し、未知物質の同定をこれまで以上にスムーズに行えます。研究者は、膨大なデータ処理に時間を割くことなく、より本質的な研究に集中できるようになります。
応用の広がり――リサイクル材から食品・香料まで
では、この装置は具体的にどのような分野・用途で利用されているのでしょうか。佐藤は「最も多い用途は未知構造物質の解析です」と語ります。
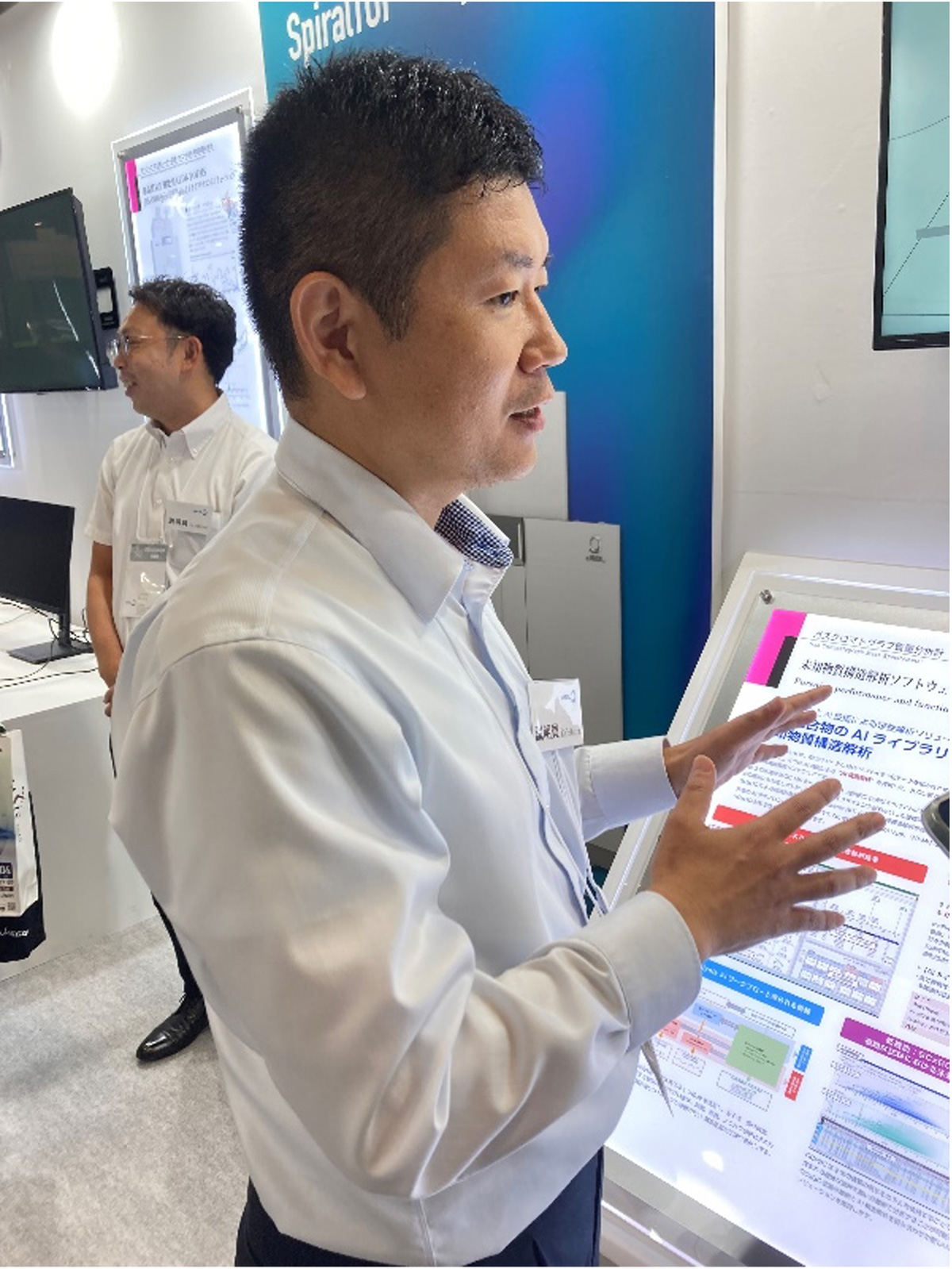
これまで利用が多かったのは材料化学分野で、高付加価値製品の品質管理やトラブル対応に欠かせない品質管理の分析に活用されてきました。近年は利用の幅が広がり、リサイクル材や食品・香料の分析でも需要が高まっています。
リサイクル材の評価では、バージン材との混合度合いや含有添加剤のバランスの崩れが最終製品の品質に影響を与えることがあります。「ポリエチレンやポリプロピレンなど身近な樹脂も、リサイクル材を混ぜると品質がどう変化するかを確認する必要があります。特に自動車業界における、欧州ELV規制では、一定割合以上のリサイクル材使用が義務化されており、その重要性は増しています」 (佐藤)
また、食品や香料の分野でも利用が進んでいます。「既知の物質はある程度把握できますが、未知物質が原因でトラブルが発生するケースでは、早期解決により製品品質向上にもつながります。未知物質を構造解析したいという要望は着実に増えています」と佐藤は語り、食品メーカーにとってにおい・香りの分析が欠かせない業務になりつつあると指摘しました。
リサイクル材や食品分野における規制強化と消費者の安全意識の高まりは、今後も装置需要を押し上げる要因となります。未知の成分を解析し、品質を向上する技術のニーズは今後も高まり続けると考えています。
未知物質構造解析ソフトウェア msFineAnalysis AI Ver.3の詳細はこちら
研究を止めないためのNMRソリューション
NMR装置を動かす際の最大の課題は液体ヘリウムです。
「液体ヘリウムの価格高騰や供給不安は、NMRの安定運用にとって深刻なリスクです。15年前は1Lあたり2,000〜3,000円だった価格が、現在は約1万円にまで上昇しています。さらに、ロシアからの輸入停止やMRI・半導体分野への優先供給により、分析分野に回らない事態も実際に起きています。」と日本電子の村田は振り返ります。
こうした背景の中、日本電子は冷媒蒸発抑制装置「CR-80」を開発しました。液体ヘリウムや窒素の蒸発を抑え、供給リスクを低減。経済性だけでなく、研究を止めないためのリスクマネジメント装置として、多くの研究現場で導入が進んでいます。

「また、冷媒蒸発抑制装置を、自社製品と組み合わせて一貫提供できる点は、日本電子ならではの強みです」と村田は語ります。サードパーティ製に頼らず、自社で責任を持って提供できる体制は、安定運用を重視するユーザーにとって大きな安心材料となっています。
「経済性というよりも、供給途絶の恐怖を避けるために導入を検討するお客様が増えています。研究を止めないことが何より大切、というお客様の意思に応えるべく、開発された装置といえます。特に、長期プロジェクトを抱える研究機関や、試料測定を途中で止められないメーカーのお客様には、ぜひ導入をご検討いただきたいですね。」 (同)
日常運転の自動化で安心を
NMR装置の安定稼働を支援するツールとしてもう一つご紹介しているのが、日常点検を自動化するソフトウェア「Delta SpecScan - Daily」です。「本ソフトウェアは、従来はユーザーにお願いしていた装置点検を自動化することで、装置管理者の負担を軽減します。また、現在の環境や設定で正確な測定が可能か判断し、必要があれば自動で再調整します。さらにログも自動収集しているため、そのログをサポート窓口に送れば一次判断を迅速に行えます」と村田は説明します。

背景には、専任オペレーターの不足があります。「1人が複数の装置を管理する現場では、NMRだけに時間を割くことがきません。だからこそ、こうした自動化はお客様に歓迎されています」 (同)。運用現場の人手不足を補い、安定した測定を支える技術として高い評価を得ています。
日本電子ならではの強みとしては、「当社は自動再調整とログ収集まで備えており、こうした点は明確な優位性といえるでしょう」 (同)。単なる自動点検機能にとどまらず、問題発生時の原因把握や復旧を効率化できる点で差別化を図っています。
現在の装置は未だ大型であることから、更新時の導入や既存装置の拡大が主流です。「小型化や低コスト化が進めば研究室単位での導入が広がり、医療応用など新しい分野への裾野拡大が期待できます」と村田は展望を示しました。
Delta SpecScan - Dailyについてのお問い合わせはこちら
まとめ
研究開発の現場では、未知物質の解明や装置の安定運用といった課題が複雑化しています。日本電子は、質量分析計による高度な構造解析と、NMRの冷媒リスク対策や自動化ソリューションを通じて、研究を止めないための包括的なサポートを提供しています。AIを活用した「msFineAnalysis AI Ver.3」による解析効率の飛躍や、CR-80による冷媒供給リスクの低減、さらにソフトウェアによる日常点検の自動化は、その象徴的な取り組みです。
「未知の構造をどう捉えるか」「装置をいかに安心して使い続けられるか」という二つのテーマに対し、日本電子はハードとソフトを一体で提供する総合力で応えています。JASIS2025で紹介した最新技術は、その姿勢を象徴するものです。
今後も、日本電子はお客様の研究開発や産業応用を支え、科学の進展と社会の課題解決に貢献してまいります。
関連記事
走査電子顕微鏡 (SEM) と透過電子顕微鏡 (TEM) の進化 自動化と高分解能で広がる可能性【JASIS2025出展レポート_Part2】
蛍光X線分析 (XRF) 装置「JSX-1000S」で切り拓く、非破壊元素分析の未来【JASIS2025出展レポート_Part3】

日本電子株式会社
日本電子は、1949年の創業以来、これまで最先端の理科学・計測機器、産業機器そして医用機器の開発に邁進してきました。
今では数多くの製品が世界のいたるところで使用され、真のグローバル企業として高い評価を頂いております。
「世界の科学技術を支えるニッチトップ企業」を目指し、ますます高度化し多様化するお客様のニーズに的確にお応えしていきます。
お問い合わせ
日本電子では、お客様に安心して製品をお使い頂くために、
様々なサポート体制でお客様をバックアップしております。お気軽にお問い合わせください。
